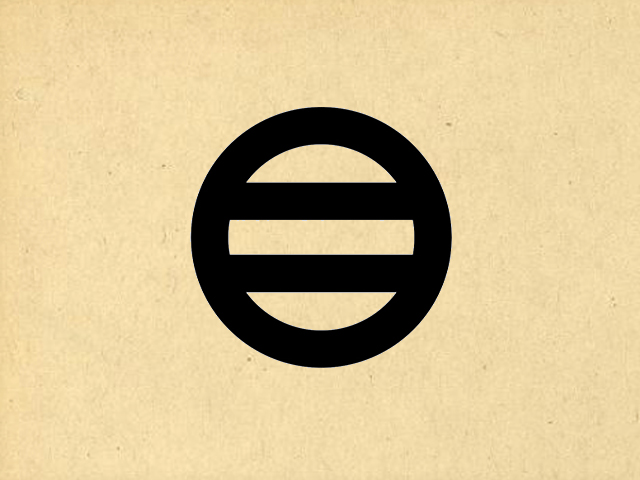「高砂屋」(たかさごや)は、他の屋号とは異なる歴史を持つ屋号です。歌舞伎界では、「中村福助」(なかむらふくすけ)という「名跡」(みょうせき:芸とともに受け継がれる芸名)は、「成駒屋」(なりこまや)の「中村歌右衛門」(なかむらうたえもん)の前に名乗る名前でした。しかし明治になって中村福助が東京・大阪の2系統に分裂した時、大阪側が採用した屋号がこの高砂屋でした。しかし、五代目高砂屋中村福助が死去すると、高砂屋の後継は途絶えてしまいます。すると、八代目成駒屋中村福助が四代目中村梅玉の名跡と、高砂屋の屋号を襲名。こうして、100年以上分裂していた中村福助の名跡は中村梅玉の名跡に統合され、高砂屋の屋号も無事受け継がれることになりました。
「高砂」とは、「能」(のう:能楽[のうがく]のひとつで、面を付けて唄い舞う舞踊)の作品。夫婦愛と長寿を願うおめでたい出し物です。

高砂屋の家紋
京都・東山の八坂神社(やさかじんじゃ)のお守りを図案化したもの。
巻物がクロスしているというデザインから、キリシタン大名(幕府から禁じられていたキリスト教を信仰した大名)やその家臣が、十字架のカモフラージュとして使用したことでも知られます。
二代目「中村梅玉」(なかむらばいぎょく)は上方(かみがた:京都・大阪)で活躍した役者です。大阪の竹田芝居(たけだしばい:からくり[糸の仕掛けで操る簡単な自動機械]による人形芝居で、幕の合間に子供芝居も行われた)で初舞台を踏み、「中村玉蔵」(なかむらたまぞう)を名乗ったのち、五代目「三枡大五郎」(みますだいごろう)の養子となって四代目「三枡他人」(みますたにん)を襲名しました。
美しく気品があり、やわらかさの底に芯の靭さ(つよさ)を秘めていると形容された芸は、1867年(慶応3年)、当時の江戸で人気を博していた名優、二代目「中村福助」(なかむらふくすけ)に認められ、弟子入りを許されます。
しかし、ここで事件が起こりました。入門直後、師匠の二代目中村福助が大阪公演中に急死してしまったのです。困った興行主が代役に立てたのが、体格の似ていた三枡他人。
こうして、三枡他人が三代目中村福助を継ぎ、高砂屋を屋号とすることになりました。ところが江戸でも二代目の弟子が三代目を襲名したため、東西で同じ名前の中村福助が存在するという事態になったのです。
とはいえ、江戸時代には有名役者が旅先で亡くなり、役者に従っていた弟子と留守を預かっていた弟子がどちらも師匠の名跡を継いだというケースは珍しくありません。そういう場合、後世の人々が先に死去した方を次代、長生きした方を次々代とするのが慣例でした。
中村福助の場合、どちらも三代目を主張したため、話がこじれてしまいます。人々は、その屋号から大阪を「高砂屋中村福助」、東京を「成駒屋中村福助」と呼んで区別していました。
その後も、三代目中村福助(高砂屋)は東京・大阪の舞台で活躍。1907年(明治40年)、大阪「角座」(かどざ:幕府から興行を許された大阪の劇場のひとつ)で、二代目中村梅玉を襲名しました。
前述したように中村福助は中村歌右衛門の前に名乗る名跡でした。つまり、三代目中村福助が中村歌右衛門を継ぐことは自然だったのですが、これ以上成駒屋との問題を大きくしないために、二代目中村梅玉を襲名したと言われています。
「梅玉」は、三代目中村歌右衛門が好んで用いた「俳名」(はいめい:俳句の作者として使用するペンネーム)でした。
二代目中村梅玉は二代目中村福助から見込まれた通り、容姿、セリフ回し、演技力のすべてに優れた名優でした。しかし大阪で初代「中村鴈治郎」(なかむらがんじろう:1860年[安政7年]~1935年[昭和10年]。成駒屋)が人気を博すようになると、自らはその相方を務め、後輩である初代中村鴈治郎の脇役に徹していました。
「近松門左衛門」(ちかまつもんざえもん:江戸中期の歌舞伎作者)作の「河庄」(かわしょう)、「伊賀越道中双六・岡崎」(いがごえどうちゅうすごろく・おかざき)、「菅原伝授手習鑑・道明寺」(すがわらでんじゅてならいかがみ・どうみょうじ)などで初代中村鴈治郎との名演が見られました。
二代目中村梅玉は初代中村鴈治郎にとっても特別の存在で、1921年(大正10年)に二代目中村梅玉が亡くなると、その落胆ぶりは近くで見ていても気の毒になるほどだったと伝えられます。

三代目中村梅玉
三代目中村梅玉は、生まれてすぐに三代目中村福助の養子になりました。5歳で初舞台を踏み、二代目「中村政治郎」(なかむらまさじろう)を襲名。
その後は、養父・中村福助と初代中村鴈治郎という上方きっての名優の演技を間近で見ながら精進し、1907年(明治40年)、父が二代目中村梅玉を襲名したのと同時に、四代目高砂屋中村福助を襲名。若手の「女方」(おんながた:女性役)として認められるようになりました。初代中村鴈治郎から女房役として指名されることが多くなったのもこの頃からでした。
1935年(昭和10年)には父と同じ三代目中村梅玉を襲名。二代目「實川延若」(じつかわえんじゃく)らとともに、初代中村鴈治郎亡きあとの上方歌舞伎を担う役者となりました。
また当時、三代目中村梅玉の芸は東京でも高く評価されており、折しも東京歌舞伎界は女方役者の世代交代期にあったこともあり、六代目「尾上菊五郎」(おのえきくごろう)や初代「中村吉右衛門」(なかむらきちえもん)らから指名されて江戸で舞台を務めることも多くなっていきました。
第二次大戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)占領下の日本に通訳として訪れた「フォービアン・バワーズ」は、大の日本通であり、歌舞伎ファンでもありました。彼は、「軍国主義を助長する」という理由で歌舞伎を廃止しようとしたGHQに対し、「歌舞伎は日本のみならず世界の文化である」と猛抗議。
1947年(昭和22年)、歌舞伎の素晴らしさを幹部にアピールするために「仮名手本忠臣蔵」(かなでほんちゅうしんぐら)の上演を歌舞伎界に求めました。この時、フォービアン・バワーズが女方に指名したのが三代目中村梅玉でした。これがきっかけとなり、歌舞伎は廃止を免れただけでなく、昭和の歌舞伎ブームへとつながっていきます。
1948年(昭和23年)に三代目中村梅玉は死去。1969年(昭和44年)にその養子、五代目高砂屋中村福助が死去すると、高砂屋の後継は途絶えてしまいました。そのため遺族が「中村福助」の名跡を成駒屋に返上することを申し出ます。
これを受けて、1992年(平成4年)に八代目成駒屋中村福助(1946年[昭和21年]~)が四代目中村梅玉の名跡と、高砂屋の屋号を襲名。こうして、100年以上分裂していた中村福助の名跡は中村梅玉の名跡に統合され、高砂屋の屋号も受け継がれることになりました。