「菊川派」(きくかわは)は、江戸時代後期の浮世絵師「菊川英山」(きくかわえいざん)を祖とする浮世絵の一派です。菊川英山が活躍した1804~1830年(文化元年~文政13年)頃は、「歌川派」と「葛飾派」という2大流派が浮世絵界を席巻。そのどちらにも属さない菊川英山でしたが、独自の個性を持つ美人画を得意として一世を風靡しました。また、菊川英山は「渓斎英泉」(けいさいえいせん)をはじめとする多くの弟子を育てたことでも知られています。菊川派の菊川英山と、最も著名な弟子の渓斎英泉にはどのような特徴があったのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

菊川英山「芸者之図」
「菊川英山」(きくかわえいざん)は、1787年(天明7年)に江戸市ヶ谷(現在の東京都新宿区)で近江屋という花屋を営む「菊川英二」(きくかわえいじ)の子として生まれました。
父の菊川英二は、日本画の一大流派「狩野派」(かのうは)の画家「狩野東舎」に師事していたため、菊川英山は父に絵を学び、次いで日本画家の「鈴木南嶺」(すずきなんれい)からも学んでいます。
さらに、「葛飾北斎」(かつしかほくさい)の門人で幼なじみの「魚屋北渓」(ととやほっけい)から葛飾派の画風を習得した菊川英山は、はじめ役者絵を手がけましたが、やがて大錦縦2枚続の美人画を考案。
17歳の頃には浮世絵師として独立し、そののち多くの美人画を描きました。
1804~1830年(文化元年~文政13年)の文化文政期に栄えた町人文化を「化政文化」と言い、浮世絵界では「喜多川歌麿」(きたがわうたまろ)や「東洲斎写楽」(とうしゅうさいしゃらく)、「鈴木春信」(すずきはるのぶ)らが活躍。ところが、化政文化が花開きはじめた1806年(文化3年)、人気絶頂のさなかにあった喜多川歌麿が病没してしまったのです。

菊川英山 作「化粧する女」
団扇絵のイメージイラスト
それでも江戸の人々は喜多川歌麿の美人画を求めてやみません。
そんなとき、団扇絵(うちわえ:団扇の絵として、または団扇の形に描かれた浮世絵版画の様式)を描くなどして知られるようになった新進気鋭の菊川英山が注目を集め、喜多川歌麿の作風に似た美人画を売り出すことになります。
人々の求めに応じて、初期こそ喜多川歌麿風の美人画を描いていた菊川英山でしたが、1810年(文化7年)頃には独自の画風を確立。
菊川英山ならではの、6頭身でほっそりとした可憐な女性像はたちまち大評判になりました。喜多川歌麿風の8頭身美人とはまた一味違う、その親しみやすさも相まって江戸市民に広く愛されたのです。
こうした菊川英山の美人画は、弟子である「渓斎英泉」(けいさいえいせん)だけでなく、「歌川国貞」(うたがわくにさだ)や「歌川国芳」(うたがわくによし)など、菊川英山以降の浮世絵師達に大きな影響を与えています。
1818年(文政元年)以降の文政期に入ると、人々の好みも変化していきました。
歌川国貞や弟子の渓斎英泉が描く、色っぽく洗練された新しいタイプの美人画が流行の中心となったのです。
流行に乗ることができなかった菊川英山は、錦絵(多色刷りの浮世絵版画)を手がけることは少なくなるものの、書物の挿絵を描いたり、富裕層の依頼で肉筆画(版画ではない一点物の浮世絵)を描いたりしています。そして、数え年81歳で没するまで、生涯作画を続けました。
菊川英山は、渓斎英泉の他、「春川英蝶」(はるかわえいちょう)や女流浮世絵師の「菊川英子」(きくかわえいし)など多くの弟子を持ちましたが、菊川英山の画風を受け継いだ弟子はいなかったと言われています。
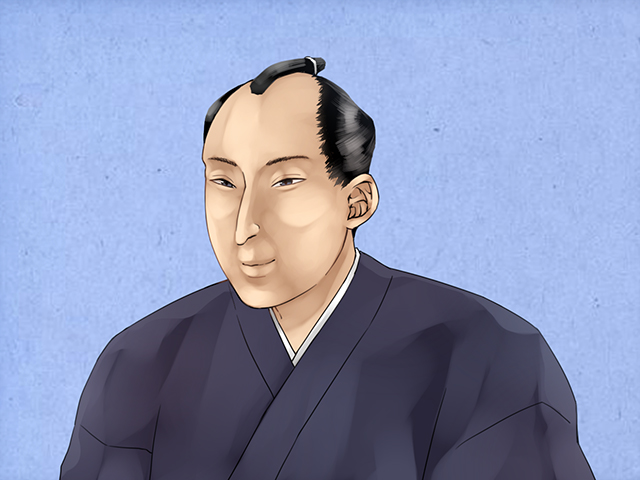
渓斎英泉
渓斎英泉は、1791年(寛政3年)に江戸星ヶ丘(現在の東京都千代田区永田町)の下級武士「松本政兵衛茂晴」(まつもとせいべえしげはる:のちに池田姓に変更)の子として誕生。父、継母、妹3人がおり、実母は6歳のときに失っています。
12歳で狩野派の奥絵師(旗本と同等の格式を持つ御用絵師)である「狩野典信」(かのうみちのぶ)の弟子「狩野白桂斎」(かのうはっけいさい)に師事した渓斎英泉。
15歳になると元服を機に安房国北条藩(現在の千葉県館山市)3代藩主「水野忠韶」(みずのただてる)の江戸屋敷に仕官します。しかし、17歳のときに上役との諍いがあり、讒言(ざんげん:他人を陥れるため、目上の者に嘘を知らせること)によって仕官先を追われ、浪人となりました。
そののち、父の知り合いからの紹介により、狂言作者見習いとして学ぶことになり、その時期には「千代田才一」(ちよださいいち)と名乗っています。
ところが、渓斎英泉が20歳になったとき、父と継母を亡くし、3人の妹を養っていくことになりました。狂言作者への道を断念した渓斎英泉は、菊川英山の門人となり、浮世絵師として働き始めます。渓斎英泉は菊川英山のもとで学びながら、家が近かった葛飾北斎のもとへも通い、独学でその画法を習得していったのです。
狂言作者になることを諦めたとは言え、文筆家であり絵師でもある渓斎英泉は、多くの艶本(好色本)を制作。22歳で最初の艶本「絵本三世相」を発表し、24歳のときには「恋の操」(こいのあやつり)を発表しています。
菊川派が得意とする美人画においては、はじめは菊川英山の影響もあり可憐な女性像を描いていました。しかし艶本を発表するようになってから、渓斎英泉の美人画は独特の艶やかさをまとうようになり、評判を取ります。美人画浮世絵師としての渓斎英泉の腕前はさらに磨かれ、1822年(文政5年)には傑作と称される「春野薄雪」(はるのうすゆき)が執筆されました。
渓斎英泉が30歳になる頃からは、庶民の恋愛をテーマにした人情本や、伝奇風の読本の挿絵も描き、「曲亭馬琴」(きょくていばきん)の伝奇小説「南総里見八犬伝」(なんそうさとみはっけんでん)の挿絵も手がけています。
また、歌舞伎三大狂言のひとつ「仮名手本忠臣蔵」(かなでほんちゅうしんぐら)を題材とした読本の挿絵も制作。当時は、大名などがかかわった実際の事件を実名で表現することは禁止されていたため、1688~1704年(元禄年間)に起こった「赤穂事件」(あこうじけん)は室町時代に置き換えて描かれました。
「刀剣ワールド財団」が所蔵する渓斎英泉作の「仮名手本忠臣蔵十一段目」は、歌舞伎のクライマックスシーンである「討入の段」を臨場感あふれる遠近法を用いて緻密に表現しています。

渓斎英泉 作「仮名手本忠臣蔵十一段目」
1829年(文政12年)、大火によって家を失った渓斎英泉は、花街で娼家(しょうか:遊女屋)の経営を始めました。また、1830~1844年(天保年間)に行われた「天保の改革」により、浮世絵をはじめとする娯楽全般に規制が設けられると、挿絵などを描くことは少なくなり文筆業に専念します。
1833年(天保4年)には「无名翁」(むめいおう)の名で、浮世絵師達の出自や師弟関係、業績などを記述した随筆「无名翁随筆」(別名:続浮世絵類考)を出版。无名翁随筆は、浮世絵を研究する上での貴重な資料として現代に伝わっています。
渓斎英泉は、「泉蝶斎英春」(せんちょうさいえいしゅん)など多くの門人を輩出し、数え年59歳でその生涯を閉じました。
【国立国会図書館ウェブサイトより】
- 菊川英山「芸者之図」


