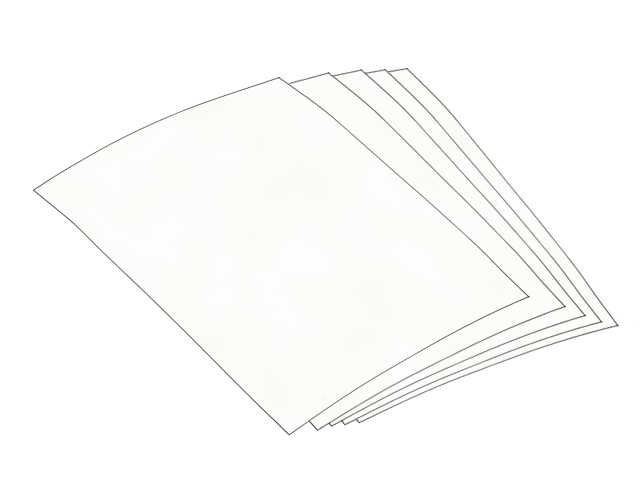日本美術を代表する浮世絵は、彩色の美しさや絵の美しさ、技術の高さなどのあらゆる面から評価され、世界中で知られています。しかし、近代化が進んだ現在の日本では、浮世絵に描かれているものに親近感が持てず、何を描いているのか分からなかったり、どこに着目して鑑賞すればいいのか分からなかったりすることも。ここでは、浮世絵を鑑賞する際に知っていればもっと浮世絵を興味深く観ることができる、浮世絵の鑑賞ポイントを紹介します。
浮世絵の鑑賞ポイントで、重要なもののひとつは、浮世絵がどのような情報を伝えているのか、どのようなものが描かれているのかを読み取ること。これらの情報を読み取ることで当時の人々の思考や多様性を知ることができる上、浮世絵に対する理解を深めることができ、当時の人々のように気軽に楽しんだり、想像したりすることができます。
浮世絵とは、江戸時代中期に流行してから明治時代に衰退するまで、階級を超えて日本中の人々に好まれた絵画で、その時代に生きる人々の日常的な生活を描いた、「風俗画」と呼ばれるジャンルの一種として登場しました。
浮世絵には日常の風景や当時の流行、人気歌舞伎役者の舞台、お祭りなどの実に様々な物が描かれており、江戸時代の人々にとっては単なる絵画ではなく、情報誌やファッション誌などの雑誌のような役割を果たしていたのです。そのため、浮世絵を鑑賞する際にまず必要なのは、技巧的な美しさを知ることではなく、どのような背景で、どのような情報を浮世絵師達が伝えようとしていたのかを理解することがポイント。
また、浮世絵のスタイルも時代によって変遷しているため、歴史を知ることで、当時の流行や情報などを知ることができるのです。浮世絵がはじめて江戸で流行しはじめたのは、1670年代のこと。現在知られる浮世絵は、多彩色を用いた「錦絵」と呼ばれるものですが、初期の浮世絵は、「墨摺絵」(すみずりえ)と呼ばれる墨1色で摺られた版画でした。
複数の色を浮世絵版画に用いはじめたのは、浮世絵が登場したおよそ100年後のこと。この間、墨摺絵に肉筆で彩色をしたり、「紅摺絵」(べにずりえ)と呼ばれる赤色と黄色、草色の3色を加えた浮世絵が流行したりしました。なお、最初期の浮世絵は本の挿絵として扱われることが一般的。このような浮世絵の歴史を知ることで、各時代の情報を知ることができ、浮世絵を鑑賞する際に楽しめるポイントが増えるのです。

東海道五十三次「日本橋」
浮世絵と言うと、多くの人がはじめに思い浮かべるのは、「葛飾北斎」(かつしかほくさい)の「富嶽三十六景」や「歌川広重」(うたがわひろしげ)の「東海道五十三次」、「東洲斎写楽」(とうしゅうさいしゃらく)の「江戸兵衛」などの世界的に有名な浮世絵がほとんど。
色鮮やかで細かな書き込みのある浮世絵は、当時の生活が垣間見えるものの他にも、クスッと笑えるような風刺画や、物語の1場面を描いたもの、観ている人を圧倒するスケールを誇るものまで様々な種類があります。これらの浮世絵は「役者絵」や「武者絵」、「物語絵」、「美人画」、「風景画」などのジャンルに分類されるのです。
例えば、富嶽三十六景や東海道五十三次は風景画や名所絵に分類され、歌舞伎役者が描かれた「江戸兵衛」は役者絵に分類されます。なお、名所絵や風景画、役者絵などは当時、観光案内図やブロマイドのような役割も果たしていました。風俗画としての浮世絵には、女性や子供、町人達が描かれた日常生活や、花火・蛍、正月などを題材とした季節ごとの様子を描いたものから、当時の風潮を皮肉るかのような風刺画まで様々な種類が混在。
また、妖怪などが描かれた「ばけもの絵」や当時の娯楽となる相撲を描いた「相撲絵」、動植物が描かれた「花鳥図」の他、「寄せ絵」や「当て字」と呼ばれるだまし絵じみた「戯画」、性的な場面が描かれた「春画」など、江戸時代の大衆文化として、浮世絵には様々なジャンルのものが誕生しました。浮世絵は、現代で言うところのマンガやイラストなどに相当し、そのため多くのジャンルの浮世絵が売られ、老若男女や階級を問わず、幅広い層に好まれていたのです。
浮世絵に何が描かれているのか、ジャンルに注目しながら鑑賞すると、より浮世絵への理解を深めることができます。
浮世絵は、絵師の名前で作品が知られていることもあり、絵師ごとの特徴を把握すると、それぞれの見どころを理解することも可能。ここでは、有名絵師ごとの鑑賞ポイントや見どころを紹介します。

葛飾北斎
生涯を画業に費やした葛飾北斎の代表作は、連作となる富嶽三十六景や「諸国瀧廻り」などの名所絵が挙げられます。葛飾北斎の描いたこれらの名所絵の特徴として、細かな書き入れや、風景の繊細な表現なども挙げられますが、重要な鑑賞ポイントとなるのは「北斎ブルー」とも称される、青色の鮮やかさです。
葛飾北斎は、18世紀後期に日本に輸入された「ベロ藍」と呼ばれる、ドイツのベルリンで発見された、従来の「藍」よりも鮮やかな染料を使って数々の傑作を描き上げました。葛飾北斎の最も有名な浮世絵のひとつ神奈川沖浪裏では、濃さの異なる3種類の青色を用いて波の陰影や奥行きを演出。透明感があり、彩度の高いベロ藍は、それまで難しかった海や空などの表現の幅を広げたのです。
また、葛飾北斎のもうひとつの鑑賞ポイントは、計算された構図の美しさ。葛飾北斎は「神奈川沖浪裏」をコンパスと定規を用いて制作したと伝わっており、大波のせり上がったこの構図は、自然界で最も美しいとされる「フィボナッチ数列」をもとにした比率と等しいとされます。なお、葛飾北斎の作品に描かれたサインも鑑賞ポイントのひとつ。
現在は葛飾北斎の名で知られていますが、雅号(がごう:絵師としての名前)を生涯に数十回も変更しました。良く知られる名は、デビュー当時に名乗った「勝川春朗」(かつかわしゅんろう)や、琳派に弟子入りした際に名乗った「俵屋宗理」(たわらやそうり)、葛飾北斎以後の「戴斗」(たいと)、「為一」(いいつ)、「卍」(まんじ)など。
浮世絵の隅には、版元の名前などの他に絵師のサインが書き入れられていますが、このサインを観ると、いつ頃の葛飾北斎が描いた絵なのかを知ることができます。
「歌川国芳」(うたがわくによし)は、「武者絵の国芳」と称されるほど武者絵を得意とした絵師として知られ、代表作となるのが中国の小説「水滸伝」(すいこでん)に登場する武将達を描いた「通俗水滸伝豪傑百八人之一個」です。
西洋の技法である「透視図法」や「解剖学」に影響を受け、写実的で臨場感のある絵を描き、一躍人気絵師となりました。歌川国芳の魅力とその鑑賞ポイントは、写実性だけでなく、写実的な風景や人物を、歌川国芳の想像力によって昇華させる、豊かな感性に溢れた絵にあります。
力強く動きのある武者絵を得意とした一方で、「宮本武蔵と巨大鯨」や「相馬の古内裏」に描かれたような、ファンタジー色の強いダイナミックな浮世絵も描いており、これも見どころのひとつ。また、歌川国芳は幕府により出版統制が発令されていた最中にも、多くの風刺画を描いた絵師としても知られています。
厳しい規制により書いてはならないとされた主題も、動物や妖怪、歴史上の偉人などに置き換えることで回避し、多くの浮世絵を世に送り出しました。歌川国芳の作品を鑑賞ポイントとして、裏に隠れた主題を探してみると、より楽しむことができます。
なお、歌川国芳は無類の猫好きとしても知られ、自宅に何匹もの猫を飼っていたと言う資料が残存。歌川国芳の浮世絵内の多くに描かれた、かわいらしい猫達も鑑賞ポイントのひとつです。
 歌川国芳「六様性国芳自慢 仏滅 保里蘭丸」
歌川国芳「六様性国芳自慢 仏滅 保里蘭丸」
所蔵刀剣ワールド財団
〔 東建コーポレーション 〕
美人画と言えば、「ポッピンを吹く女」や「寛政三美人」など、多くの日本人が「喜多川歌麿」(きたがわうたまろ)の名前を挙げるほど、喜多川歌麿は美人画の分野で最も人気となった浮世絵師。美人画が有名な浮世絵師として、「鈴木春信」(すずきはるのぶ)や「鳥居清長」(とりいきよなが)なども挙げられますが、喜多川歌麿が描いた美人画の最大の特徴とその鑑賞ポイントは、描かれた女性達のしぐさやその表情。
武者絵や合戦絵などに見られる力強い躍動感と比べると、喜多川歌麿の描く美人画に用いられる線は細く滑らかなものが多く、女性的な美しさが表現されています。また、目線や首の傾げ方、指先に至るまで細やかな配慮がされており、全体的な奥ゆかしさが感じられるのです。
喜多川歌麿の美人画には「大首絵」と呼ばれる、人物の上半身を描いた構図が取り入れられ、その背景には、雲母(うんも)を粉末状にした雲母(きらら)を絵の具に交えて塗るなど、オリジナリティに溢れています。喜多川歌麿の鑑賞ポイントは、内面からにじみ出るような女性の美しさを表現した美人画やそのオリジナリティにあると言えるでしょう。
なお、美人画の鑑賞ポイントとして、髪型や着物などを見比べてみることがおすすめ。当時流行したファッションやおしゃれなどを知ることができ、より浮世絵を楽しむことができるのです。
浮世絵の重要な鑑賞ポイントのひとつとして、描かれた題材や卓越した絵を楽しむのはもちろんのこと、錦絵の多彩な鮮やかさや精緻な彫の細やかさ、陰影の美しさなどにも着目することができます。
浮世絵は、完成するまでに浮世絵師だけでなく、絵師の描いた線通りに版木を彫る「彫師」や、彫られた版木を印刷する「摺師」といった職人が携わり、分業で制作されていました。彼らの職人技も、浮世絵の美しさの一端を担っているのです。
 あてなしぼかしの例 「藤原保昌月下弄笛図」
あてなしぼかしの例 「藤原保昌月下弄笛図」
所蔵刀剣ワールド財団
〔 東建コーポレーション 〕
マイクロの単位で彫られた髪の毛や細かな表情の動き、布の細かい柄など、熟練した彫師による精密な技術は浮世絵の見どころのひとつ。また、摺師の技巧を凝らした色彩の鮮やかさなどに着目するのも鑑賞のポイントとなります。
雲や空を表す際に良く用いられた、色の濃さを変化させ、グラデーションを入れる「ぼかし」と言う技術は、摺師入魂の妙技。浮世絵の最上部に見ることが多い帯状のぼかしを「一文字ぼかし」と言い、ぼかしを入れる部分に水気を与えることで独特なグラデーションを入れます。
また、明確な形を決めず、絵の具をにじませるように制作するぼかしは「あてなしぼかし」と言い、「月岡芳年」(つきおかよしとし)の「藤原保昌月下弄笛図」における雲などの表現に用いられました。その他、色を使わず、版木に深く掘った模様を紙の裏から押し出して模様のみを摺り出す、現代で言うところのエンボス加工となる「空摺」(からずり)と呼ばれる技法も、彫師や摺師の腕前が光って見える、鑑賞ポイントと言えます。